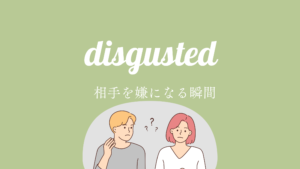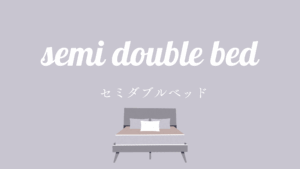「好きだから同棲する」というのは自然な流れのように見えますが、実際には「好き」だけでは乗り越えられない問題も。
生活を共にしていない恋人同士だった頃には気にならなかった相手の生活習慣や金銭感覚、家事に対する価値観の違いは、ひとつ屋根の下で暮らすことで一気に顕在化します

特に昨今では、リモートワークによって一日中一緒に過ごす時間が増えたり、物価高騰の影響で家計のやりくりがシビアになったりと、同棲生活を取り巻く環境は年々ハードルが上がっています。
そんな中、改めて注目されているのが「同棲契約書」です。
契約書と聞くと堅苦しく感じるかもしれませんが、これは二人の関係を縛るためのものではなく、よりよい関係を築くための設計図と捉えるとしっくりきます。
曖昧だった生活のルールを明文化し、将来のトラブルを未然に防ぐための大切なツールとして、20代〜30代を中心に浸透し始めています。

私たちについて
大学生時代から付き合いを始め、交際5年でようやく同棲開始。東京23区内に在住(1DK)。
同棲から数か月でプロポーズ → そこから半年後に入籍。
クロ(彼氏)
経営者|ブログ歴5年|飽き性
シロ(彼女)
会社員|ホテル・カフェ巡り好き|よく寝る
本記事でわかること・読み進め方
本記事では、以下のような内容を詳しく解説していきます。
- 同棲契約書の基本知識…そもそも法的効力はあるのか? 他の文書との違いは?
- 作ることで得られるメリット…金銭トラブルや家事の不公平感をどう解決できるか?
- 実際の作り方とテンプレート…初心者でも迷わず作成できる手順と書き方のポイント
- 活用事例とよくある失敗例…実際に契約書を活用したカップルの声と改善策
読み終える頃には、「二人だけの同棲ルールを作ってみよう」と思えるような、実用的かつ前向きなヒントが得られるはずです。
同棲契約書とは?
そもそも同棲契約書とはなんなのでしょうか?
正直私自身もこの記事を書こうと思うまでは全く知らない言葉でしたので、確認してみます。
法的効力はあるの? 民法との関係
同棲契約書は、民法上「当事者間の自由な合意」に基づく契約書として扱われます。
要は個人間で結べる契約書(=約束)という認識でいいと思います。
日本の法律では、たとえ婚姻関係にない二人であっても、金銭の貸し借りや所有物の取り決めなどが明確に記された契約は有効とされます。
さらに、公証役場で公正証書にしておくことで、金銭面のトラブルが起きた場合に裁判所を通じた強制執行も可能になります。
ただし、同棲契約書には婚姻に伴う扶養の義務や相続権などは発生しません。
これは戸籍上の「夫婦」ではないためであり、例えば医療同意や遺産の相続には別途対応が必要になります。
▶ ワンポイント:金銭トラブルの防止を目的とするなら、公正証書化+具体的な金額明記が鉄則!
覚書や同棲協定との違い
一見似ている文書である「覚書」や「協定」とは、目的や効力が異なります。下記の比較表をご覧ください。
| 呼称 | 目的 | 法的効力 | よく使われる場面 |
|---|---|---|---|
| 同棲契約書 | お金・家事・生活ルール全般 | 中〜高 (公正証書で高) | 長期同棲、事実婚を想定 |
| 覚書 | 特定の事実の確認 | 低〜中 | ペット・家具の所有者確認 |
| 同棲協定 | 行動指針や価値観の共有 | 低 | 話し合いベースでの合意 |
特に同棲協定は、ルールというよりも「約束」や「二人の価値観の共有」が主眼に置かれます。
一方、同棲契約書は「現実的な生活に必要な取り決め」を主に記載する実務的な書類です。
契約書を作るカップルの実態とは?
最近では、同棲前に「契約書を作っておこうか」と提案するカップルが増えています。
各サイトを調べた結果、下記のようなデータが見られました。
- 契約書を作った経験があるカップル:18%
- 作成タイミング:同棲開始前に作成:67%/同棲半年以内に作成:24%
- 作成の主な理由:金銭トラブル防止:62%/家事分担の明確化:51%/別れる時の手続きを簡素化したい:33%
数字からもわかる通り、実用性を重視して契約書を活用するカップルが着実に増えています。
同棲契約書を作成するメリット
金銭トラブルを未然に防ぐ
同棲を始めるとまずぶつかりやすいのが「お金の問題」です。
家賃、光熱費、食費、日用品、インターネット代……一つひとつの金額は大きくないように見えても、支払い方が曖昧なままだと「いつも自分ばかり払っている」といった不満が蓄積されます。
同棲契約書では、それらの支出を具体的に分担し、支払日や金額の記載も盛り込むことで、お互いに透明性のある関係を築くことができます。
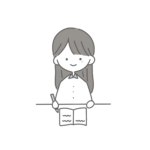
ちなみに私たちはすべて私が管理しています!
家事の偏り・不満を可視化し解消
「洗濯は誰がする?」「ゴミ出しは交代制?」など、日々の生活に密着する家事も、同棲を始めてから悩みの種になりがち。
特に仕事が忙しい時期や体調を崩したときなどは、家事の偏りが大きなストレスにつながることもあります。
契約書に「何曜日に誰が何をするか」「週に何回担当するか」などを記載することで、口約束になりがちな家事分担を見える化できます。
ただし、私たちのように「家事の役割分担を明確にしていない」カップルも多いと思います。
「相手を思いやり、必要な時に気付いた方が行う」ことができれば明確なルール設定は不要だと思いますよ!
別れるときの損害や手続きコストを抑える
悲しいことですが、全ての同棲がゴールインするとは限りません。
別れの際、引っ越し費用や家具の所有権、敷金礼金の取り扱いなど、現実的な問題が数多く発生します。
契約書に「持ち出す家具・精算方法」や「立ち退きにかかる費用分担」などを記載しておけば、感情に左右されずスムーズな解決が可能になります。
これは、破局後も最低限の信頼を保った関係を築くために非常に有効な手段です。
結婚生活のシミュレーションになる
同棲契約書は、いわば結婚生活の予行演習です。
収入と支出を管理し、家事を分担し、生活のルールを決めて暮らすことは、夫婦生活において必要不可欠な要素。
同棲期間中にこれらを体験し、記録として残しておくことで、結婚後にありがちな「こんなはずじゃなかった…」を防ぐことができます。
同棲契約書に記載すべき必須項目
では、具体的に同棲契約書に記載すべき事項とはなんなのでしょうか?
具体的な例文を記載しつつ確認していきます!
家賃の分担と支払い方法
同棲生活で最も大きな固定費となるのが「家賃」です。
契約書には、家賃の分担比率(例:6:4、5:5など)と、誰が契約者になるのか、どちらの口座からいつ支払うのかを明記しましょう。
また、敷金・礼金・更新費用の分担や、途中解約時の負担についても取り決めておくと安心です。
例文:「家賃は月額100,000円とし、甲が60%(60,000円)、乙が40%(40,000円)を、毎月25日までに甲名義の口座へ振り込む。」
生活費の項目と分担割合
水道光熱費、食費、日用品、通信費などは「生活費」として分類されますが、ここも曖昧になりがちな部分です。
各項目の支払い方法を明確にし、共通口座を作る場合はその用途も記載しておきましょう。
例文:「電気・ガス・水道・インターネット代はすべて甲の口座から支払い、乙は毎月月初に生活費30,000円を負担する。」
家事の役割分担
どんなに仲が良くても、「家事の分担」は日々の生活に直結するため、必ず話し合っておくべきです。
週ごとのローテーション制にするか、固定の役割を決めるかなど、お互いに無理のない形で設計しましょう。
例文:「洗濯と掃除は甲、料理とゴミ出しは乙が主に担当し、状況に応じて柔軟に協力する。」
共同貯金や将来の資金計画
結婚資金や引っ越し費用など、将来を見据えた貯金ルールも盛り込むことで、目的意識を共有できます。
目標金額や積立のペース、使う場面の定義などがあると具体性が増します。
例文:「共通口座に毎月15日に各自10,000円ずつ積立て、用途は結婚式・新生活資金とする。」
貴重品・高額家電の所有と精算ルール
テレビ、冷蔵庫、洗濯機など高価な家電や家具を共同購入する際は、所有者の明記や別れるときの扱いについても決めておくと、トラブル防止に繋がります。
例文:「冷蔵庫は甲の購入とし、破損時や同棲解消時には甲に返却または残存価値で乙が買い取る。」
同棲契約書の作り方4ステップ
ステップ1:話し合いと項目の洗い出し
まずはふたりで、どのようなルールや取り決めが必要かをざっくばらんに話し合うところから始めましょう。
家計、家事、生活習慣、来客ルールなど、普段気になっていることをリストアップします。
Googleスプレッドシートや付箋アプリなどを使うと、視覚的に整理しやすくなります。
ステップ2:文面を作成
ゼロから作るのは大変なので、ネットに落ちているようなテンプレートを活用するのがおすすめです。
ChatGPTなどのAIを活用することも有効ですが、曖昧な表現が含まれる場合があるので、必ず最終確認をしましょう。
例:生活費欄に「食費:甲6割/乙4割」のように具体的に書き込む
ステップ3:文言の最終確認と調整
作成した契約書は、必ずふたりで再確認し、わかりづらい表現や不平等に感じる部分がないかをチェックします。
感情的な言葉や抽象的な表現(例:「なるべく」「適宜」など)は避け、「◯円」「週2回」など数値を用いた明確な記述にすることが重要です。
ステップ4:署名・押印と保管
紙で作成する場合は2部印刷して、日付・署名・押印を行い、双方が1部ずつ保管しましょう。
電子契約ツール(CloudSign、GMOサインなど)を使えば、オンラインで署名・保管でき、印紙税もかからずスマートに管理できます。
よくある質問(FAQ)
Q. 契約書はどのタイミングで作成すればいい?
A. 同棲開始前に作成するのが理想ですが、すでに同棲している場合でも遅くありません。むしろトラブルの芽が出た段階で話し合うことが大切です。
Q. 法的効力を強めるにはどうすればいい?
A. 公証役場で「公正証書」として作成することで、金銭面に関する条項は法的強制力を持つようになります。費用は1〜3万円程度です。
Q. 破棄や更新は自由にできる?
A. 契約書には「改定条項」や「更新時期」を設けておくのがおすすめです。半年〜1年ごとに話し合って見直しましょう。
さいごに
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。
内容に不安がある場合は、弁護士や行政書士など専門家にご相談ください。